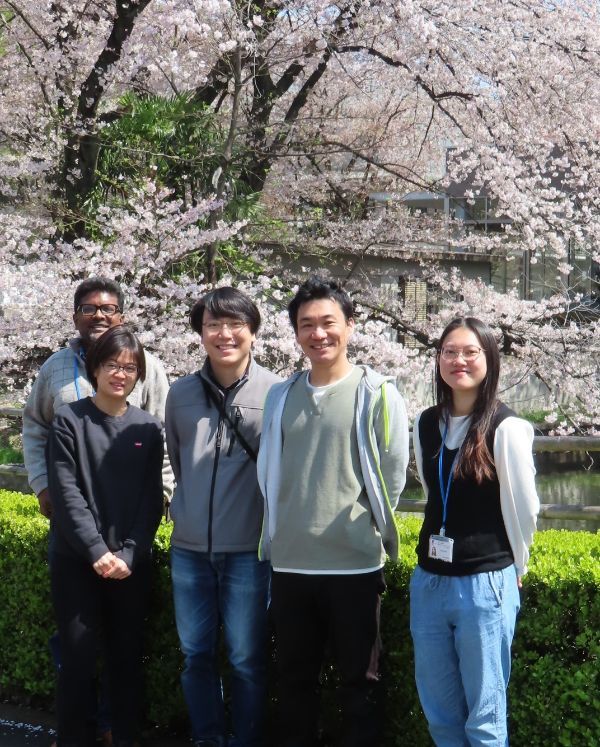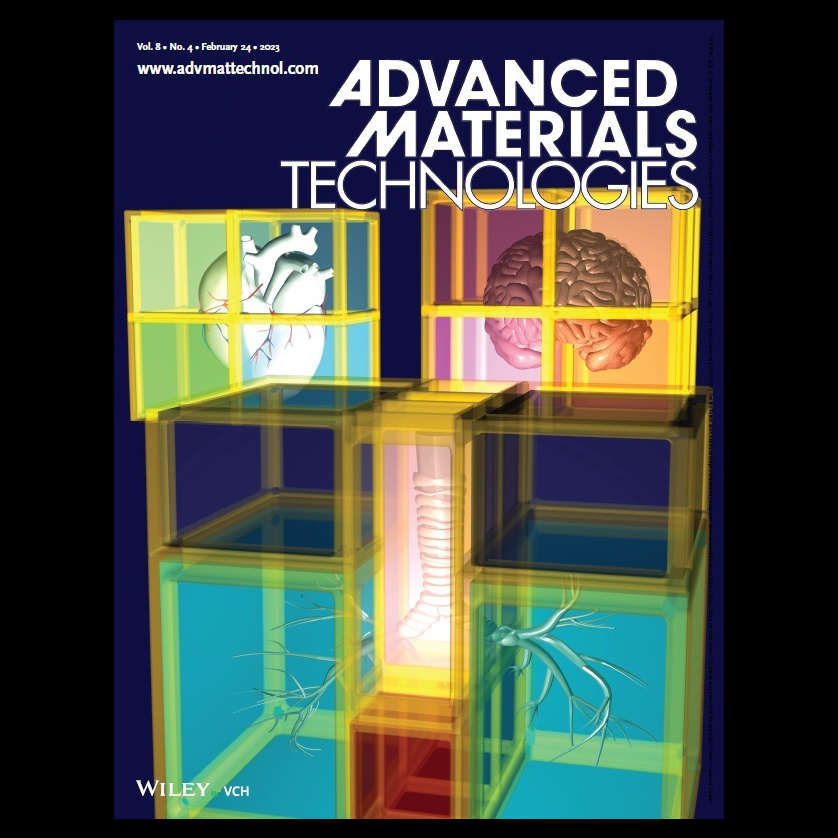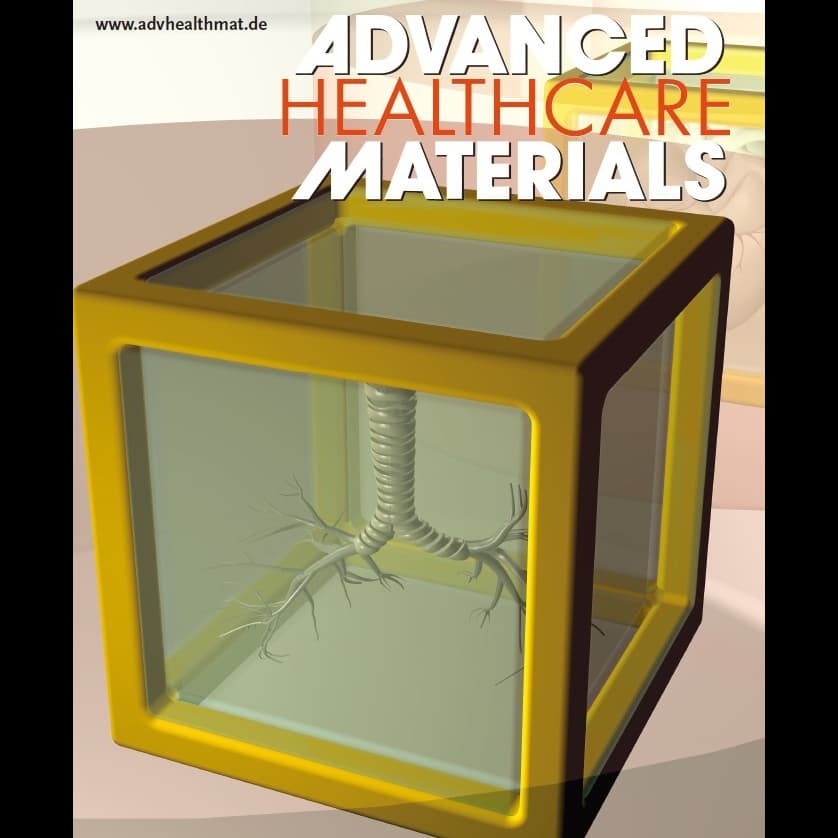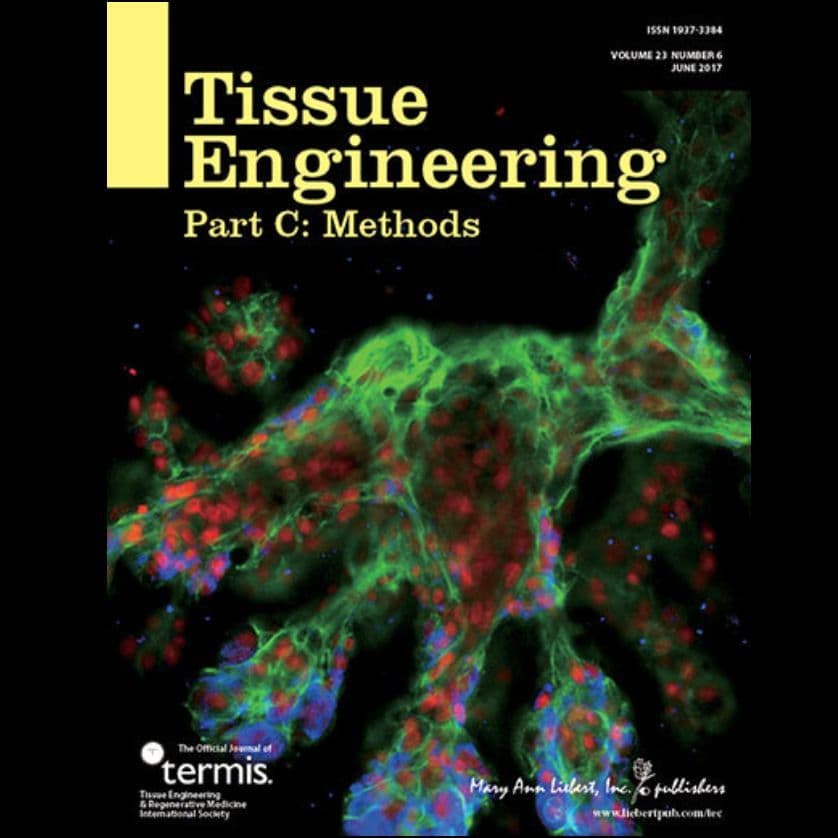動画
研究内容をより分かりやすく視覚的に理解してもらうため、発表済みの研究を動画にして再編集しています。
ヒトの細胞を用いた新たな非臨床試験モデルとして、オルガノイドと臓器チップ(Organ-on-Chip)は欧米を中心に世界中で開発が進められている一方、両技術を同時に組み込むシステムは実験が複雑になりすぎ、実用化に大きな壁が存在しています。私たちが開発したシステムは,オルガノイドを始めとする三次元組織をCube型の培養器にモジュール化することで、オルガノイド培養の技術をマイクロ流体チップに取り入れることが可能なシステムを確立でき、臓器チップを「誰でも簡単に」実装できるプラットフォームとして期待できます.
各種細胞組織を予めCube内で作成しておくことで,複数のオルガノイドを自在な組み合わせ、細胞間・組織間相互作用を表現可能なin vitro実験モデルシステムを構築し,薬物動態試験,安全性試験,薬効薬理試験など医薬・機能性食品・化粧品など様々な分野で利用可能なシステムの開発を目指しています.
本研究では、CUBE型の培養器内でオルガノイドに特定因子の濃度勾配を与える「Gradient-in-CUBEシステム」を開発しました。本システムを用いて、iPS細胞塊から、恣意的な方向に神経外胚葉と中胚葉の分子マーカーが局在するオルガノイドを作製しました。作製したオルガノイドは、与えた濃度勾配の方向を見失うことなく解析が可能であり、オルガノイド培養から体軸方向付与・解析までシームレスな実験ワークフローを確立することができました。オルガノイド培養のプラットフォームとして広く活用されることを期待します。
今回、3Dプリンターを用いてL字型のフレームを持つ培養器を作製し、異なる性質を持つ複数のゲル(マトリゲルなど)を、表面張力を利用して空間的に自在の位置に配置するキューブ型の培養プラットフォーム「MultiCUBE」を開発しました。簡単なピペット操作で異なる複数のゲルを自在に配置し、細胞に対して空間情報が与えることができるようになります。これによりオルガノイドを生体により近い複雑な構造の環境下で成長させることが可能になりました。
細胞周囲の細胞外マトリックスがどのように細胞行動に影響を与え、また細胞自身も細胞外マトリックスに影響を及ぼしているのかを調べるため、マトリゲルを細胞の上から被せた場合とそうでない場合で細胞行動をトラッキングしました。すると細胞が通った後の一部には痕跡が残されており、同じ道を他の細胞も追随していることが分かりました。この道を三次元的に染色して観察すると細胞がECMにトンネルと作っていたことが分かりました。これらの結果から、細胞は周囲にある細胞外マトリックスから抵抗を受けて動きを制限されているものの、時間経過とともにこの周囲からの抵抗を弱めることで細胞外マトリックス内に通りやすい道を自ら作り出して、他の細胞もその道を積極的に通るということが分かりました。
上記の実験結果を細胞とECMとの物理的なやり取りにより、細胞がECMからの抵抗を壊しながら進むと仮定して、数理モデルを構築すると、シミュレーション結果と実験結果が一致することが確認できました。ということは、細胞周囲に抵抗が大きい箇所と小さい箇所を混在させることにより、細胞の移動方向をコントロールできるのではと仮説を立てました。この仮説を立証するため、細胞集団の隣接する一方向のみに、磁気ビーズを置いて永久磁石により磁気ビーズを動かしてECMの抵抗を弱めた箇所を作成して細胞行動を観察すると、予想通り抵抗の弱い方に積極的に細胞が移動していくことが、実験・理論両方で確認できました。
ディッシュ上では一見ランダムに動いているように見える細胞も、集団形状を厳密に決めるといつも同じ動き方をすることが分かります。例えば気管支上皮細胞集団を三角形になるように微細加工を用いて配置すると、必ず細胞は最初三角形の頂点方向に移動し、跳ね返って三角形を再構築したのちに頂点付近から最初に三角形の外に出ていくという、非常にユニークかつ再現性の高い動き方をします。常に同じ動き方をするということは、そこに細胞が動く方向を決定するためのルールが存在しているはずです。それを仮説して数理モデルに落とし込むことができれば、実験だけでは見えなかった時空間変化を今度はシミュレーションから解析できるようになるので、細胞の行動をロジカルに理解することができるようになります。
十分な硬さを持ちつつ栄養成分だけを通す網目構造をもつゲルの壁で囲まれたCube型培養器内で細胞を三次元培養することにより、立体形成に必要な基質ごと培養中のサンプルをピンセットで容易に持ち上げたり回転させたりすることが出来るようになりました。このハンドリングの良さを生かすことにより、様々な工学技術をCubeの中に詰め込むことができるようになります。例えば、これまで低倍レンズを用いて全体を見ながら高感度にイメージングすることが困難でしたが、このCubeを用いてサンプルを回転させることにより、6方向からスキャンを行うことができるため、同じ顕微鏡・同じサンプルでもイメージングの質を飛躍的に向上させることができました。
気管支上皮細胞をマトリゲル内で分散させて培養しても、シスト構造を有するだけで分岐は発生しません。しかし、この気管支上皮細胞をゲル内の一か所に集めてやると、一旦細胞は凝集したのちに分岐を発生します。さらに周囲に血管内皮細胞であるHUVECを分散させて培養すると、長期間に渡り大域の分岐構造を発生することが分かりました。この実験系で経時変化を確認すると、分岐構造の過程で、細胞は1)凝集、2)リーダー細胞の発生、3)リーダー細胞の消失と分岐の収縮、4)細胞のスパイラル行動による分岐伸長、5)分岐の維持、といった様々な動き方が確認できました。
論文カバーアートなど
Photos